音楽活動をしていると、制作、SNS更新、ファン対応、データ管理など、多岐にわたる業務に追われがちです。
「もっと時間をクリエイティブな作業に使いたいのに、雑務が多すぎる…」
そんな悩みを抱えるアーティストや音楽活動者に注目されているのが、自動化ツール「Make(旧Integromat)」です。
Zapierと並ぶ人気ツールですが、両者には得意分野の違いがあります。本記事では、Zapierと比較しながらMakeの強みを解説し、音楽活動にどう活かせるかを具体例を交えて紹介します。
Makeとは?Zapierとの基本的な違い
Makeは、複数のアプリやサービスを連携させ、業務を自動化するプラットフォームです。
- Zapierは「Aが起きたらBを実行する」という直線的なワークフローが得意。
- Makeは「ノード(丸いアイコン)」を線でつなぐ視覚的UIで、複雑な分岐や並列処理を自由に組み立てられるのが特徴です。
音楽活動のように、SNS、メール、スプレッドシート、ストリーミング関連のツールなどを同時に扱う場面では、Makeの柔軟性が光ります。
Makeの強みとZapierとの違い
1. 視覚的に複雑なワークフローを構築できる
Zapierは一方向に進むシンプルな構造ですが、Makeでは「もし条件Aならこの処理、条件Bなら別の処理」といった分岐が簡単に作れます。
音楽活動では「ファンの登録内容によって通知先を変える」「複数SNSに同時投稿する」などが直感的に実現可能です。
2. 高度なデータ処理機能
Makeはワークフローの中でデータを加工できます。
例えば
- フォームから送信されたメールアドレスを自動で正規化
- Spotify再生データを集計してGoogleスプレッドシートに反映
こうした「ただ繋ぐだけでなく、データを整える」機能は、Zapierより強力です。
というようなことができます。
3. コスト効率の良さ
Zapierは「タスク」単位で課金されますが、Makeは「オペレーション」単位です。
同じ処理を行った場合、複雑なワークフローほどMakeの方がコスト効率が高いケースが多くなります。
音楽活動における具体的な活用例
ファン・データ管理の自動化
ファンからのフォーム回答を受け取った際
- 内容によって自動でGoogleスプレッドシートに振り分け
- 担当メンバーにSlack通知
- メール返信も条件付きで自動送信
といった一連の流れをMakeで完結できます。
リリースやイベント準備の効率化
新曲リリースをトリガーに
- X(旧Twitter)、Instagramへの自動投稿スケジュール作成
- 関係者へメール通知
- プレスリリースのGoogleドキュメント下書きを自動生成
など、複数の作業を一度の設定でまとめて進められます。
無料版と有料版の違い
無料版
- 月1,000オペレーションまで利用可能
- Zapierと違い、マルチステップのワークフローを無料で構築できるのが大きな魅力
有料版(Coreプラン /月〜)
- 実行間隔の短縮(最短1分ごと)
- データフィルタリング機能
- チームでの共同編集
音楽チームで活動している場合は、早めに有料版を検討する価値があります。
まとめ
ZapierとMakeはどちらも便利な自動化ツールですが、使い分けのポイントは以下です。
- Zapier:シンプルな連携をサクッと実装したい人向け
- Make:無料でも複雑なワークフローを組みたい人、音楽活動の業務全体を自動化したい人向け
まずは無料版を試して、自分の活動にどれだけ効果があるか体感してみましょう。業務効率化に成功すれば、音楽活動により多くの時間を割けるようになります。
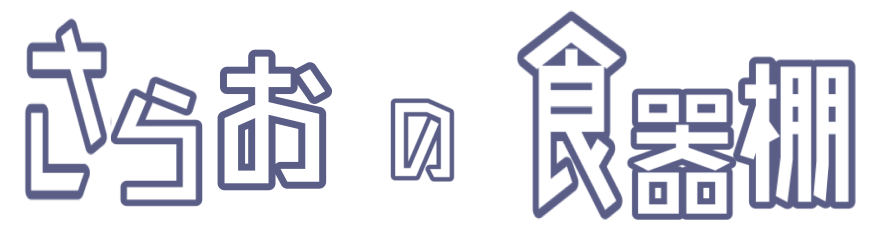
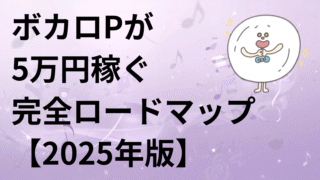

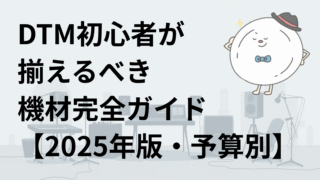
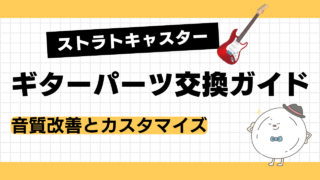
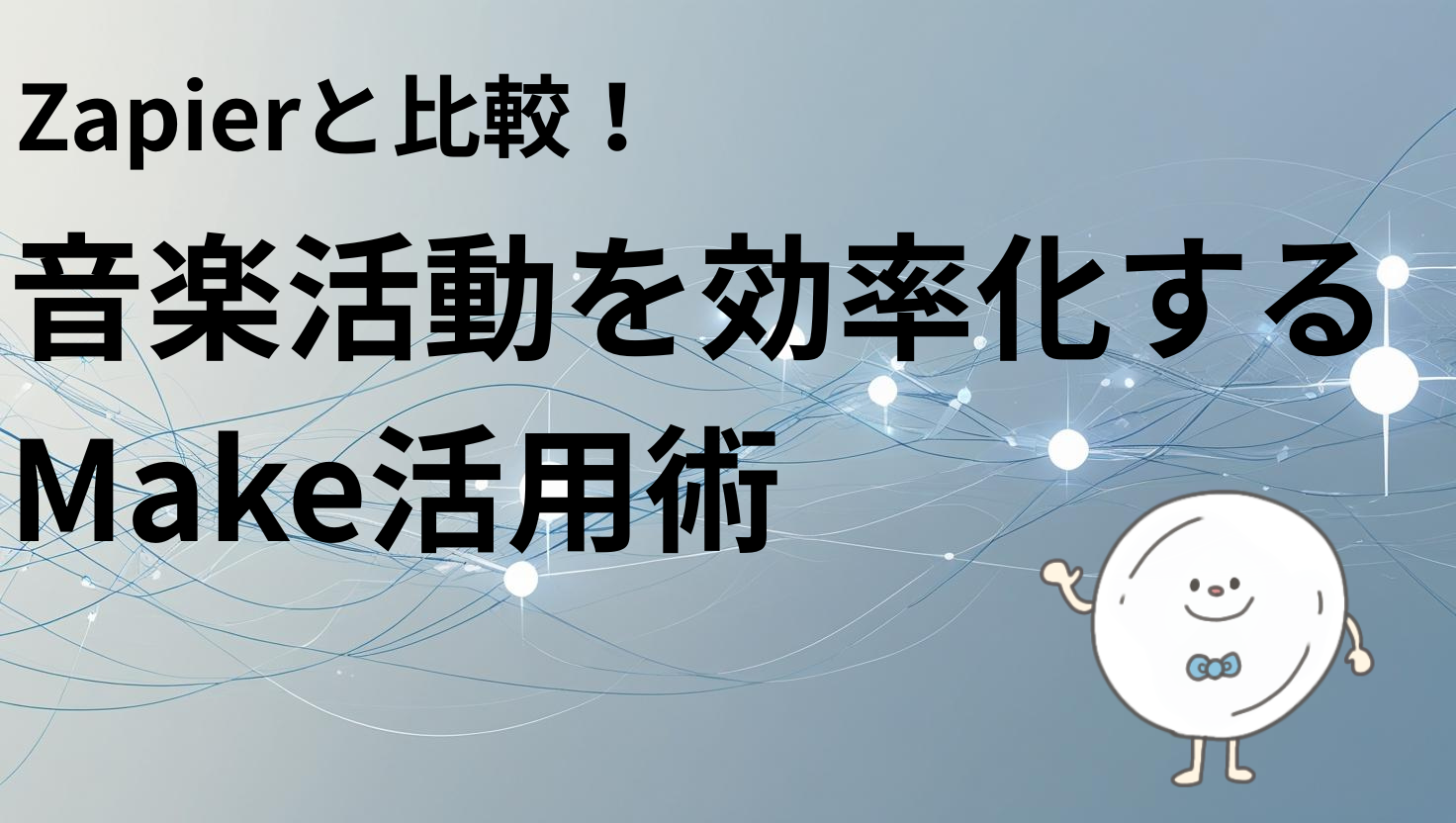
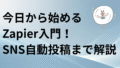
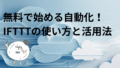
コメント