ライブ会場で聞く不思議な声の正体
ライブ会場やスタジオで、本番前にスタッフやアーティストが「チェック・ワン・ツー」「ツェー」「ハー」といった独特な言葉を発しているのを耳にしたことはありませんか?
一見すると意味不明に思えるこれらの言葉ですが、実は音響エンジニアにとって非常に重要な意味を持つ、科学的根拠に基づいた「音のテスト」なのです。
この記事では、マイクテストで使われる特殊な言葉の意味と、それぞれがどんな音響チェックに役立っているのかを詳しく解説します。
マイクテストの言葉にはすべて意味がある
マイクテストで使われる言葉は、単なる習慣ではありません。それぞれの発音には、異なる周波数帯域や音量レベルが含まれており、PA(音響)エンジニアがマイクやスピーカーの状態を総合的にチェックするための重要なツールとなっています。
高音域をチェックする言葉
「ツェー」「シー」「チェック」
これらの言葉には摩擦音や破擦音が含まれており、2kHz〜8kHz程度の高周波成分が豊富です。
特に「ツェー」や「シー」は、マイクの高音域の感度をチェックするのに最適です。また、ハウリング(ピーッという異常音)が発生しやすい高音帯域を事前に確認し、イコライザーで調整するためにも使われます。
英語の「Check(チェック)」も同様に、硬い音や高音のチェックに有効で、世界中のライブ会場で定番のフレーズとなっています。
低音域と音量をチェックする言葉
「ハー」「ワン」
「ハー」は息を多く使う発音のため、低音域(100Hz〜300Hz程度)や音の厚みをチェックするのに役立ちます。さらに、マイクに息が吹き込まれた時に発生する「ポップノイズ」の確認にも使えます。
英語の「One(ワン)」は、比較的低音で音量が大きめの音をチェックするのに適しています。低音がしっかり出ているか、音が割れずに出力されるかを確認できます。
「ツー(トゥー)」
「Two(ツー)」は高音寄りの発音で、小さな音量でもしっかり拾えるかをチェックします。「ワン・ツー」と続けることで、低音から高音まで一通りの確認ができるのです。
その他の特殊なフレーズ
「本日は晴天なり」
放送業界でよく使われるこのフレーズは、元々は試験電波を発射する際の総務省令に基づく言葉でした。現在は廃止されていますが、滑舌や安定したトーンで発声できるため、今でもスタジオでのマイクチェックに使われることがあります。
ただし、音響的な調整効果は限定的で、どちらかといえば伝統的な習慣として残っているフレーズです。
ライブスタジオでよく使われるマイクテストの言葉一覧
実際のライブ現場では、以下のような言葉が状況に応じて使い分けられています。
| 言葉 / フレーズ | 主なチェック目的 | 音響的な意味 |
| チェック・ワン・ツー | 総合的なバランスチェック(最も一般的) | 「チェック」: 硬い音や高音(2kHz〜4kHz辺り)の確認。ハウリングが起こりやすい帯域。 |
| ワン | 低音・音量(大) | 低い音域(100Hz〜300Hz辺り)の確認。音量が大きく突出しないか、低音がしっかり出るか。 |
| ツー (トゥー) | 高音・音量(小) | 高い音域(4kHz〜8kHz辺り)の確認。小さい音でもしっかり聞こえるか、高音でハウらないか。 |
| ツェー / シー | 高音・歯擦音 | 摩擦音・破擦音に含まれる高周波成分をチェック。特にマイクの高音感度や、耳に痛い高音がないかを確認。 |
| ハー / ハッ | 低音・息の音・音量(突発的) | 息の吹き込み(ポップノイズ)のチェック。また、突発的に大きな音が入った時に音が割れないか(ピークレベル)の確認。 |
| ヘイ | 音程・声のトーン | 声の高さを変えながら発音し、高音から低音まで一通りバランスが取れているかを確認。 |
| テス / テスト | 動作確認 | 単純にマイクが生きているか(音が出ているか)の確認。 |
| (単発の)チェッ、チェッ | 高音・反応 | 瞬時にマイクのレスポンス(反応)や、高音域のハウリング傾向を確認。 |
なぜこれらの言葉が重要なのか
ライブやレコーディングでは、会場の広さ、形状、機材の種類、アーティストの声質などによって、最適な音響設定が異なります。
マイクテストは、PAエンジニアがこれらの要素を総合的に判断し、本番で最高の音質を届けるための準備作業です。「ツェー」や「ハー」といった特殊な言葉を使うことで、短時間で効率的に複数の周波数帯域をチェックでき、ハウリングや音割れなどのトラブルを事前に防ぐことができるのです。
まとめ:マイクテストは音響の科学
一見すると不思議に聞こえる「ツェー」や「ハー」といったマイクテストの言葉は、実は高度な音響理論に基づいた合理的なチェック方法です。
それぞれの言葉に含まれる周波数特性を利用して、マイクやスピーカーの状態を素早く正確に把握できるよう設計されています。
次回ライブ会場でこれらの言葉を耳にした時は、「今、プロが最高の音を作るために科学的なチェックをしているんだな」と思って見守ってみてください。きっとライブがより楽しくなるはずです。
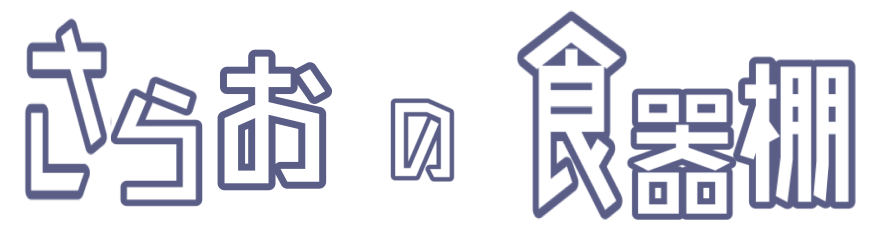
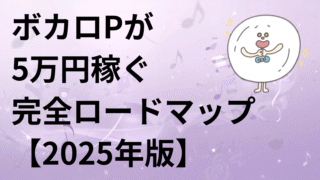

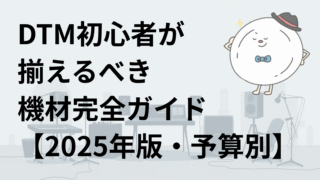
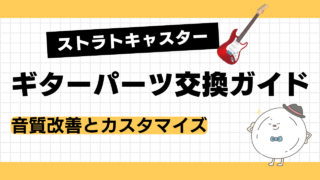
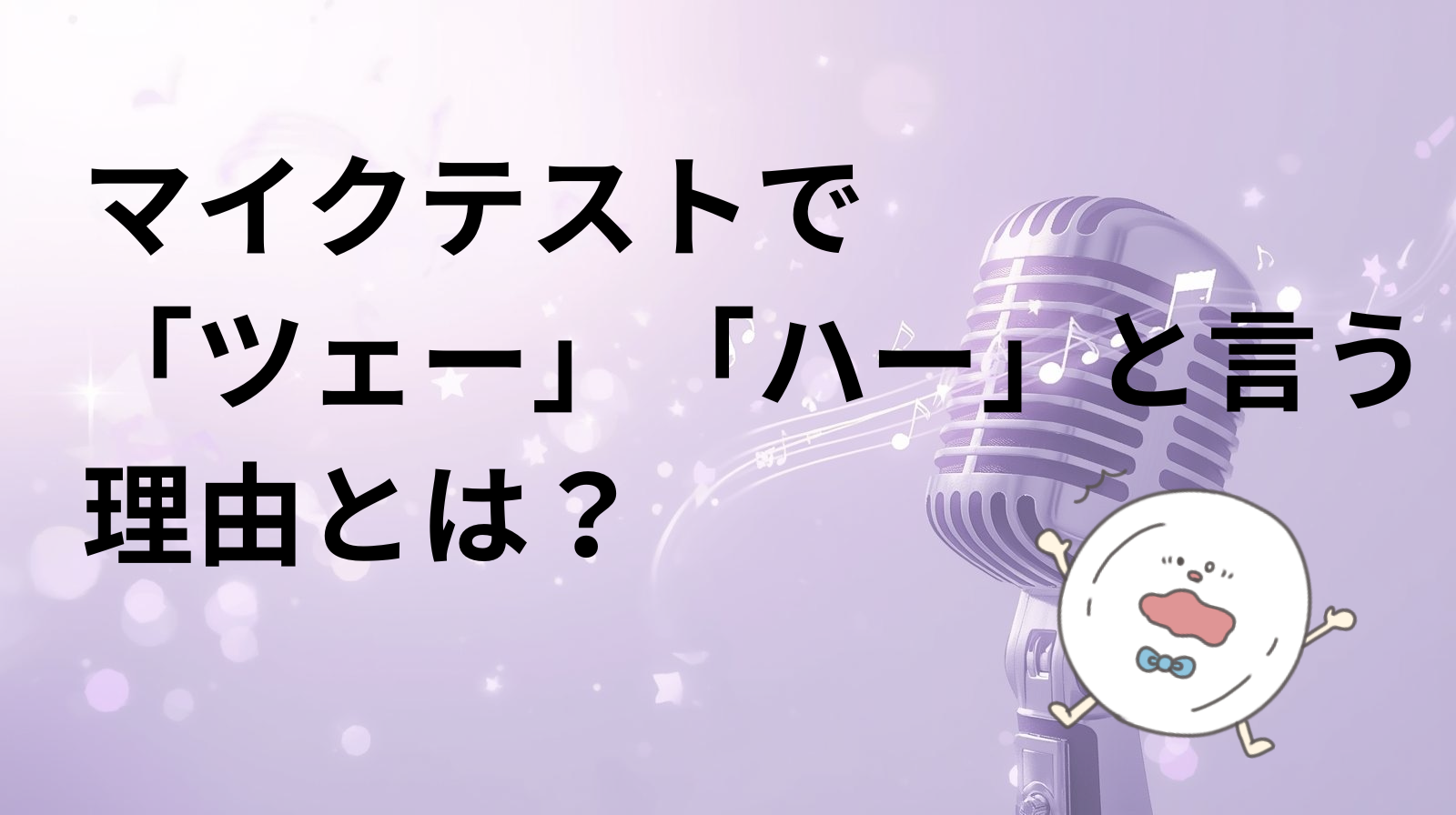
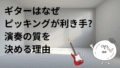
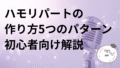
コメント