音楽制作やオーディオの世界では、「ドンシャリ」「フラット」といった言葉と並んで「かまぼこ」という表現が使われることがあります。
この「かまぼこ」とは、食べ物の話ではなく、音の周波数バランスを表す専門用語の一つです。しかし、現代の音楽制作において、このバランスは本当に必要なのでしょうか?
本記事では、「かまぼこ」型EQの特徴から、現代における位置づけまで、詳しく解説していきます。
「かまぼこ」とは?周波数バランスの基礎知識
音の周波数バランスを表す3つの表現
イコライザー(EQ)で音を調整する際、その結果として得られる音のキャラクターを表す代表的な表現が3つあります。
かまぼこ型 中音域(ミッドレンジ)が最も強調され、低音・高音が控えめなバランスです。音が明瞭で聞き取りやすい反面、低音の迫力や高音のきらびやかさは少なくなります。
ドンシャリ型 低音域(ドン)と高音域(シャリ)が強調され、中音域が控えめなバランスです。迫力があり、きらびやかで派手な音になり、現代的なロックやダンスミュージックに多く見られます。
フラット型 すべての周波数帯域が均一に再生される平坦な特性です。自然で色付けがない音で、ミキシングやマスタリング時の判断基準として理想とされています。
「かまぼこ」が生まれた背景
「かまぼこ」型の周波数バランスは、過去の技術的な制約から生まれました。
1950年代から1970年代のラジオ放送やモノラル環境では、低音や高音を十分に再生できる機器が少なかったため、最も重要な情報である歌詞やメロディを確実に届けるために、中音域を強調する必要があったのです。
当時のオールド・ジャズ、フォーク、ソウルミュージックなどに、この傾向が顕著に表れています。
現代における「かまぼこ」EQの位置づけ
現代音楽制作での標準バランス
現代のプロフェッショナルなマスタリングでは、フラットに近い自然なバランスが理想とされています。
高音質が求められる現代では、低音の土台、中音の存在感、高音のきらびやかさという全帯域のバランスが整っている状態を目指します。リスナーは高性能なヘッドホンやスピーカーで音楽を聴くことが多く、迫力や解像感のある音が求められているからです。
ストリーミング時代の音質基準
SpotifyやApple Musicなどのストリーミングサービスでは、ラウドネスノーマライゼーション(平均音量の統一)が行われます。
「かまぼこ」のように特定の帯域にエネルギーを集中させても、配信プラットフォーム側で音量調整されるため、ダイナミクスが失われた平坦な音として再生されてしまう恐れがあります。
「かまぼこ」を意図的に使う場面
レトロなサウンドの再現
あえてローファイ(低忠実度)な懐かしい音の質感を出したい場合、「かまぼこ」型のバランスは有効です。
ヴィンテージ感を演出したいアーティストや、特定の時代感を表現したい楽曲では、意図的にこのバランスを採用することがあります。
ボーカル・楽器の明瞭性重視
ボーカルやアコースティックギターなど、中音域が主体の要素を聴き手に最も明瞭に届けたい場合にも活用できます。
このバランスにすると、他の帯域に埋もれず、音が前に出てくる効果があるため、ストーリーテリング重視の楽曲では選択肢になり得ます。
特定の再生環境への最適化
小型スピーカーや古いラジオなど、低音や高音の再生能力が限られた環境で確実に情報を伝えたい場合にも有効です。
ただし、これは現代の一般的な音楽リスニング環境では稀なケースと言えるでしょう。
現代音楽における最適解とは
全帯域バランスの重要性
現代のミキシングでは、緻密な作業により楽器ごとの分離や音場(ステレオイメージ)を追求しています。
マスタリングで「かまぼこ」にしてしまうと、中音域に音が密集しすぎて、せっかく作り込んだ楽器ごとの空間や奥行きが潰れてしまう恐れがあります。
ダイナミクスを活かした音作り
適度なダイナミクスを保ち、配信基準に合ったラウドネスを持つサウンドが、現代の高音質な音楽の条件です。
極端な帯域強調を避け、楽曲本来の表現力を最大限に引き出すことが、プロフェッショナルなマスタリングの目標となっています。
まとめ
「かまぼこ」型のEQバランスは、過去の技術的制約や特定の再生環境で音を最大限に明瞭にするための工夫として生まれました。
現代の音楽制作においては、全帯域でバランスが取れたフラット寄りのサウンドが主流です。ただし、レトロな音像や特定の意図を強調したい場合には、「かまぼこ」は今でも有効な選択肢となります。
目指す音楽の時代感や音のキャラクターに合わせて、適切な周波数バランスを選択することが、現代のクリエイターに求められるスキルと言えるでしょう。
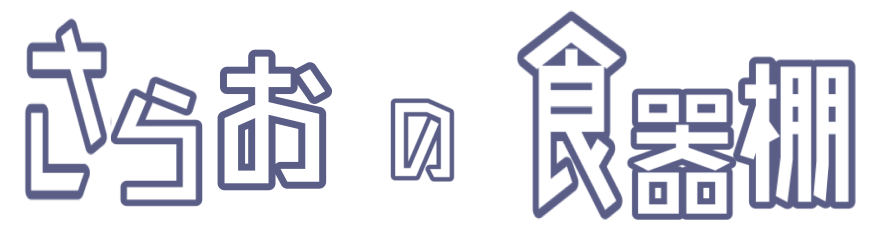
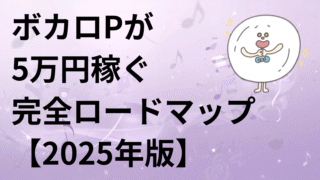

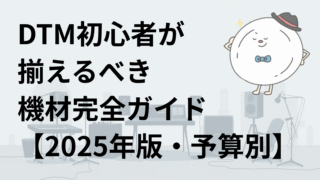
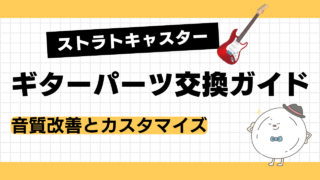
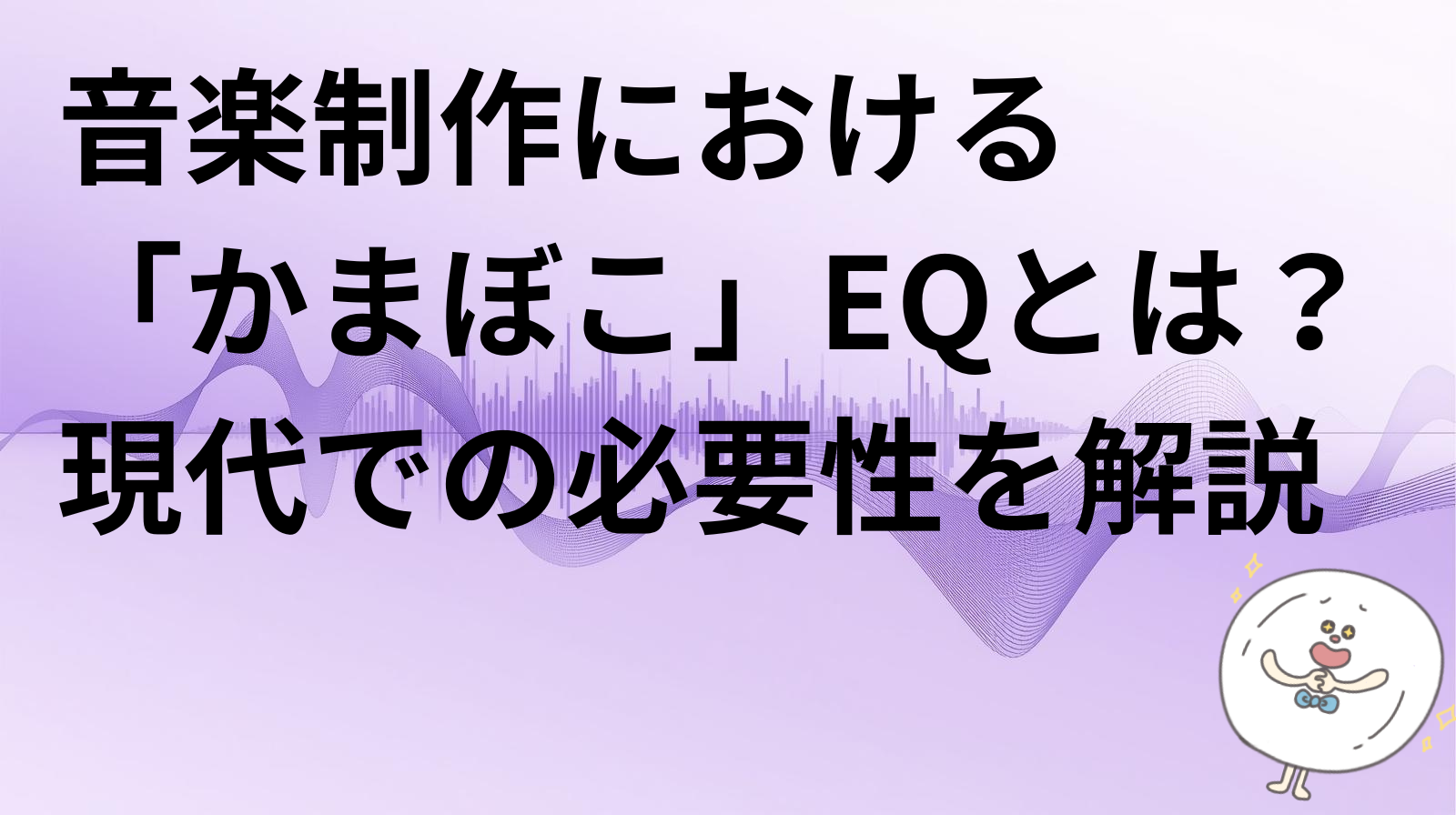
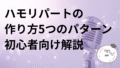
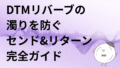
コメント