音楽を聴いているとき、「このメロディー、どこかで聴いたことがある」と感じた経験はありませんか?それは、多くの楽曲で使われている「定番のコード進行」が原因かもしれません。
コード進行とは、曲の中で和音(コード)が移り変わっていく流れのこと。実は、ヒット曲の多くには「王道」と呼ばれる共通のコード進行が使われています。
今回は、J-POPをはじめとする多くの楽曲で使われる有名なコード進行を8つ厳選してご紹介します。これらを知ることで、音楽をより深く楽しめるようになるはずです。
王道進行:J-POPサビの定番
ディグリーネーム: IV→V→IIIm→VIm
Cメジャーでのコード: F→G→Em→Am
王道進行は、J-POPのサビで最も頻繁に使われるコード進行です。「4536進行」とも呼ばれ、キャッチーで高揚感を生み出すのが特徴。一度聴いたら忘れられないようなメロディーを作るのに最適です。
代表曲として、ZARDの『負けないで』、スピッツの『ロビンソン』、YOASOBIの『怪物』などがあります。聴いてみると、サビの盛り上がりに王道進行が使われていることが分かるでしょう。
カノン進行:感動を呼ぶ最強の進行
ディグリーネーム: I→V→VIm→IIIm→IV→I→IV→V
Cメジャーでのコード: C→G→Am→Em→F→C→F→G
カノン進行は、パッヘルベルのクラシック曲『カノン』に由来する、壮大で感動的なコード進行です。切なさと美しさを同時に表現できるため、「最強の進行」とも呼ばれています。
KANの『愛は勝つ』、あいみょんの『マリーゴールド』など、心に響く名曲に多用されています。結婚式のBGMとしても人気が高いのは、この進行が持つ感動的な響きのためです。
小室進行:疾走感と切なさの融合
ディグリーネーム: VIm→IV→V→I
Cメジャーでのコード: Am→F→G→C
1990年代に小室哲哉さんが多用したことから名付けられた小室進行。「6451進行」とも呼ばれ、切ない疾走感が特徴です。マイナーコードから始まることで、どこか哀愁を帯びた雰囲気を醸し出します。
TM NETWORKの『Get Wild』、LiSAの『炎』のサビなど、エモーショナルな楽曲に使われることが多い進行です。
丸サ進行:おしゃれでアンニュイな響き
コード例: FM7→E7→Am7→Gm7→C7
椎名林檎さんの『丸の内サディスティック』で有名になった丸サ進行。「Just The Two of Us進行」とも呼ばれ、ジャズやシティポップのような洗練された雰囲気が特徴です。
非ダイアトニックコード(その調にないコード)を含むため、他の進行にはない独特のおしゃれさがあります。Adoの『うっせぇわ』、MISIAの『つつみ込むように…』などでも使われています。
王道ポップ進行(レリビー進行):シンプルで普遍的
ディグリーネーム: I→V→VIm→IV
Cメジャーでのコード: C→G→Am→F
王道ポップ進行は、ポップスに最適なシンプルで親しみやすい進行です。ビートルズの『Let It Be』に使われたことから「レット・イット・ビー進行」「1564進行」とも呼ばれ、「いつメン」という愛称もあります。
スピッツの『チェリー』のサビとイントロ、イルカの『なごり雪』のAメロ、マルーン5の『She Will Be Loved』など、時代を超えて愛される名曲に使われています。
4156進行:哀愁の浮遊感
ディグリーネーム: IV→I→V→VIm
Cメジャーでのコード: F→C→G→Am
4156進行は、哀愁を帯びた浮遊感が特徴の進行です。「J-POP進行」とも呼ばれ、現代のヒット曲で頻繁に耳にします。
YOASOBIの『夜に駆ける』のBメロとサビ、米津玄師の『Lemon』のサビなど、最近の人気曲に多用されています。どこか儚げで、心に残る印象を与えるのが魅力です。
コード進行を知ると音楽がもっと楽しくなる
これらの定番コード進行を知っておくと、音楽の聴き方が変わります。「あ、この曲は王道進行だ」「ここでカノン進行を使っているのか」と気づくことで、曲の構造や作り手の意図が見えてくるのです。
作曲に興味がある方にとっては、これらの進行は強力な武器になります。まずは定番の進行を使って、自分なりのメロディーを乗せてみてください。多くのヒット曲がこれらの進行をベースにしているのですから、あなたも名曲を生み出せる可能性は十分にあります。
まとめ
今回ご紹介した8つのコード進行は、音楽の世界で長年愛されてきた「黄金パターン」です。
- 王道進行:J-POPサビの定番
- カノン進行:感動を呼ぶ最強の進行
- 小室進行:切ない疾走感
- 丸サ進行:おしゃれでジャジーな雰囲気
- 王道ポップ進行(レリビー進行):シンプルで普遍的
- 4156進行:哀愁の浮遊感
これらの進行を意識して音楽を聴くと、新しい発見があるはずです。また、作曲に挑戦したい方は、まずこれらの進行を使ってみることをおすすめします。
音楽理論は難しく感じるかもしれませんが、実際には多くの名曲が同じような構造で作られています。コード進行という「共通言語」を理解することで、音楽の世界はもっと広く、深く、楽しいものになるでしょう。
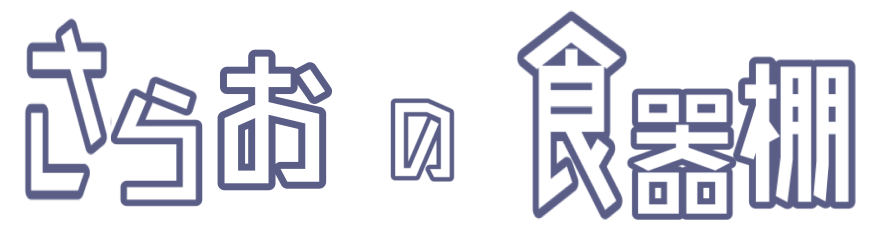
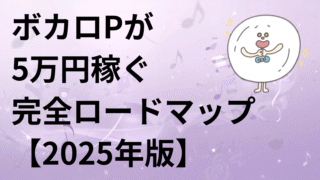

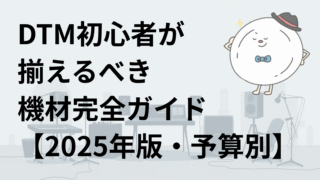
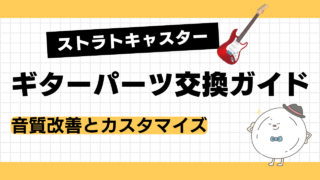
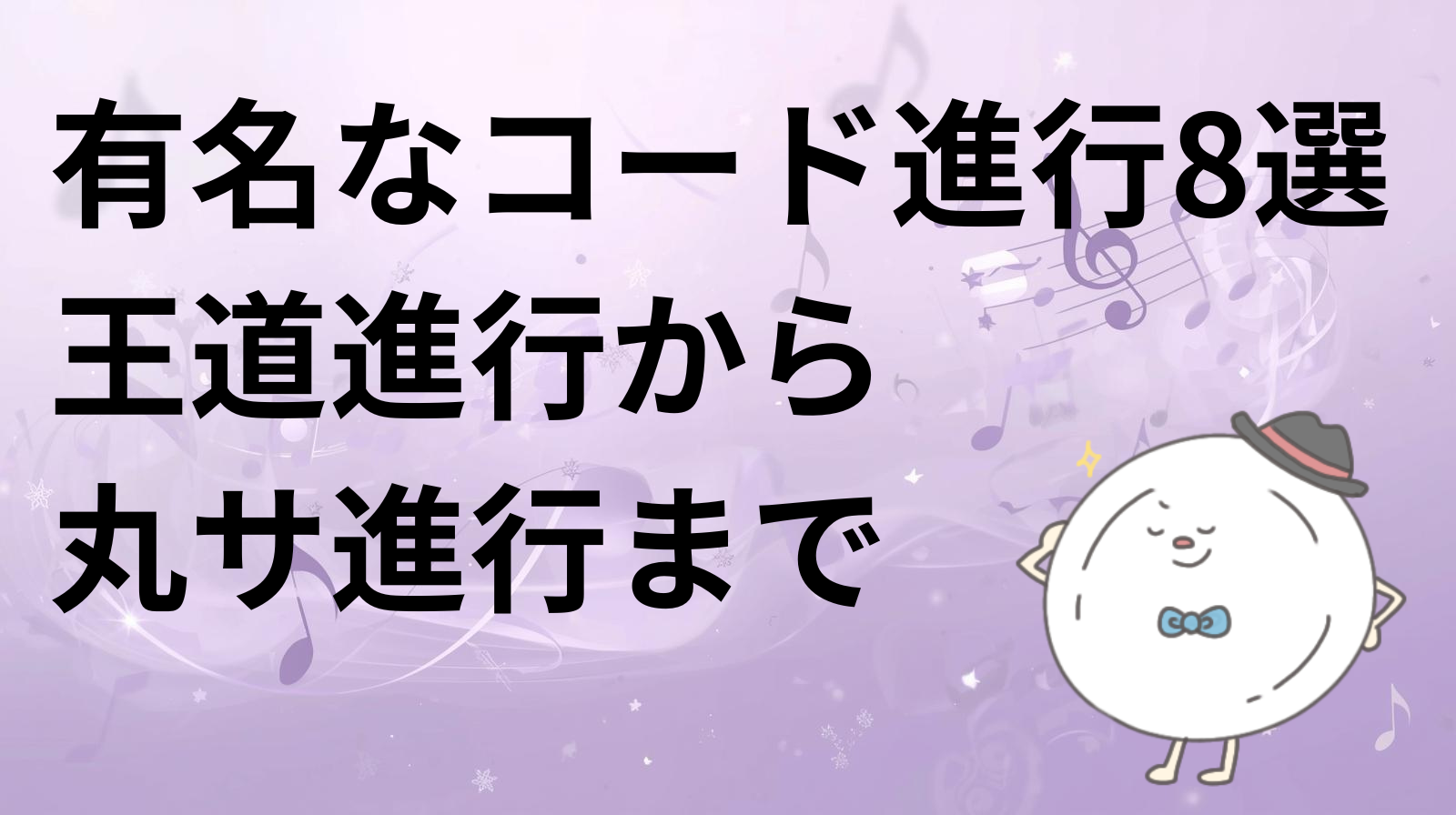
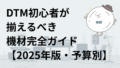
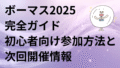
コメント