オリジナル曲を作りたいけれど、「詩から書くべき?」「メロディが先?」「コードから始める?」と迷っていませんか?
実は、作曲の順番に絶対的な正解はありません。しかし、キャッチーで印象に残る楽曲を作りたいなら、サビのメロディから作り始める方法が最も効果的です。
この記事では、作曲における様々なアプローチを比較しながら、なぜサビのメロディ先行が優れているのか、その理由と具体的な手法を解説します。
作詞と作曲、どちらを先に始めるか
ボーカル曲を作る際、最初に直面するのが「歌詞を先に書くか、メロディを先に作るか」という選択です。それぞれのアプローチには明確な特徴があります。
詞先(しせん)のメリットとデメリット
詞先とは、歌詞を先に完成させてから曲をつける方法です。
メリット:
- 伝えたいメッセージを深く、自由に表現できる
- 言葉の制約を受けず、情景や感情を細部まで描写できる
- 初心者にとって、最初に何をすべきか明確で取り組みやすい
デメリット:
- 完成した歌詞にメロディを後付けするのが難しい
- 字余りや字足らずが発生しやすい
- 言葉に合わせるとメロディが単調になりがち
曲先(きょくせん)のメリットとデメリット
曲先とは、メロディや音楽を先に作ってから歌詞をつける方法です。
メリット:
- メロディや雰囲気を重視した曲作りができる
- キャッチーなサビやリズム感のある曲を作りやすい
- 先に曲の構成や尺が決まるため、制作がスムーズ
デメリット:
- 完成したメロディに言葉を乗せるのが難しい場合がある
- 伝えたいメッセージがメロディに引っ張られ抽象的になることも
題先(だいせん)という第三の選択肢
題先とは、曲のタイトルやテーマを最初に決めてから、それに沿って作詞・作曲を同時進行する方法です。部分ごとに順番を入れ替えながら柔軟に制作を進められます。
メロディとコード、どちらから作るか
曲先を選んだ場合、さらに「メロディ」「コード」「リズム」のどれから手をつけるかという選択肢があります。
メロディ先行
鼻歌やハミングでメロディを先に作り、その後に合うコードをつける方法です。
向いている人: メロディのひらめきを重視したい人、オリジナリティを追求したい人
コード先行
ピアノやギターでコード進行を先に決め、その上でメロディを考える方法です。
向いている人: コード理論を重視したい人、楽器経験者
リズム/リフ先行
特徴的なドラムパターンやベースライン、ギターリフを先に作る方法です。
向いている人: ダンスミュージックやロックなど、グルーヴ感を重視したい人
なぜメロディ先行がキャッチーな曲を生むのか
私はメロディ先行こそ、最もキャッチーな楽曲を生み出せる方法だと考えています。その理由は2つあります。
音楽の「顔」を最初に作るから
メロディは楽曲の中で最も人間の感情に直接訴えかけ、記憶に残りやすい部分です。コードはメロディを支える土台ですが、リスナーが「この曲だ」と認識するのはメロディです。
最初にメロディをしっかり構築することで、曲のフック(引っかかり、魅力的な部分)を最大限に活かすことができます。
コードの制約を受けない自由な発想
コード先行で作曲すると、意識的か無意識的かにかかわらず、コードの響きや進行パターンにメロディが引きずられ、パターン化しやすい傾向があります。
一方、メロディ先行では、コードの制約から解放された状態で、純粋に「良い響き」「歌いやすいリズム」「感情を動かす音の動き」を追求できます。結果として、コード理論からは生まれにくい、斬新で印象的なメロディが生まれやすくなります。
コードは後から「メロディを最も魅力的に響かせる伴奏」として機能させることで、シンプルな和音や意外性のあるテンションコードなど、攻めた選択が可能になります。
サビのメロディから作り始める最強のアプローチ
メロディ先行の中でも、私が最も推奨するのが**「テーマ → サビのメロディ → その他」という順番**です。
サビのメロディから作る3つの強力なメリット
1. 曲の核(テーマ)がブレない
サビは、その曲で最も伝えたいメッセージや感情が凝縮される場所です。最初にサビのメロディを固めることで、曲のムード(明るさ、切なさ、激しさなど)やエネルギーの最高地点が明確に定まります。
その後、AメロやBメロを作る際も、「このサビに向けてどう盛り上げていくか?」という明確な指針ができるため、途中で曲の方向性を見失うことがありません。
2. モチベーションと創作エネルギーを最大限に活かせる
作曲は、始めた直後が最もモチベーションが高く、インスピレーションが湧きやすい状態です。最も重要なサビに、この最高のエネルギーを注ぎ込むことで、最高のクオリティのサビを生み出すことができます。
重要度の低いAメロやイントロから始めて途中で疲れてしまうと、肝心のサビの出来が妥協されてしまうリスクがあります。
3. 他のパーツを逆算して作りやすい
サビという「ゴール」が決まっていれば、AメロやBメロは「サビを際立たせるための加速台や物語の導入」としての役割が明確になります。
- Aメロ: サビとの対比のために、落ち着いた低い音域や緩やかなリズムで世界観を描く
- Bメロ: サビに向けて音域を少しずつ上げたり、リズムに変化をつけたりして緊張感を高める
このように、後のパートはサビという絶対的な基準を元に、対比や展開を意識して設計でき、全体としてストーリー性のある構成に仕上がりやすくなります。
サビのメロディをより印象的にするポイント
キャッチーなサビを作るために、以下のテクニックを意識しましょう。
- 曲中の最高音をサビに持ってくる: 多くのヒット曲では、サビで最も高い音を使用します。これにより、リスナーは「盛り上がっている」と直感的に感じます
- 音を大きく跳躍させる: 低い音から一気に高い音へ飛ぶフレーズを入れることで、強いインパクトとドラマチックな展開を生み出せます
- フレーズの反復を意識する: 短いフレーズを繰り返したり、メロディのリズムパターンを強調したりすることで、記憶に残りやすくなります
歌詞は最後に、メロディのリズムに合わせる
私の場合、歌詞は最後に、メロディに合わせたリズムの詩をつけることができるため、この方法を採用しています。
メロディに歌詞を合わせる3つの強み
1. 最高のグルーヴ(ノリ)を損なわない
最初に作ったサビのメロディは、音の高さだけでなく、音の長さやアクセントが最高の状態で組み合わさってできています。歌詞を後からこのグルーヴにぴったり合わせることで、リスナーは「心地よいノリ」や「歌いやすさ」を強く感じます。
詩先で言葉のリズムが先に決まると、メロディがそのリズムに縛られ、ノリが悪くなることがあります。
2. 歌詞の制約に縛られない自由なメロディ
先に言葉を置いてしまうと、どうしてもその「言葉の意味」や「文法的な流れ」にメロディが引っ張られてしまいます。しかし、先にメロディを作れば、音の響きや展開を自由に追求でき、誰も思いつかないような独創的なメロディラインを生み出すことができます。
3. 言葉を楽器のように扱える
メロディに後から歌詞をはめる作業は、言葉を「音色」や「リズムの要素」として扱っていることになります。
例えば、メロディの速い部分には子音が多い言葉を、メロディが長く伸びる部分には母音が響く言葉や、メッセージが強く伝わる核となる言葉を選ぶことで、言葉を「意味」と「音」の両面からコントロールできます。
まとめ
作曲の順番に絶対的な正解はありませんが、キャッチーで印象に残る楽曲を作りたいなら、「テーマ → サビのメロディ → その他のメロディ → 歌詞」という流れが最も効果的です。
この方法なら、曲の核となるサビをブレずに作り上げ、最高のモチベーションで最高のクオリティを実現できます。また、メロディのグルーヴを損なわず、自由で独創的な音楽表現が可能になります。
もしあなたが今から曲作りを始めるなら、まずは「得意なこと」「わくわくすること」から始めてみてください。慣れてきたら、あえて普段と違う順番を試すことで、新しい個性が生まれることもありますよ。
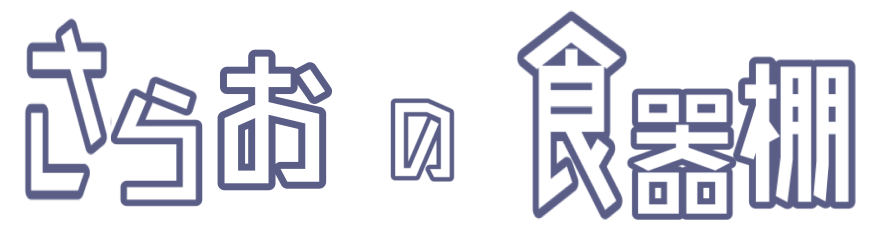
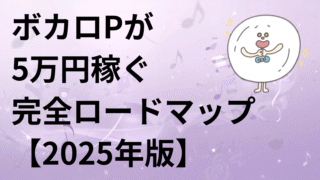

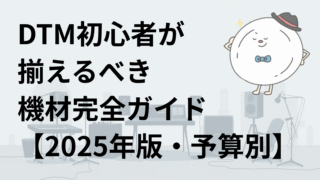
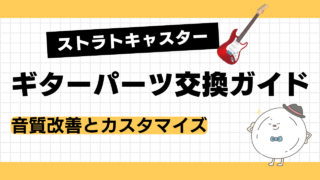
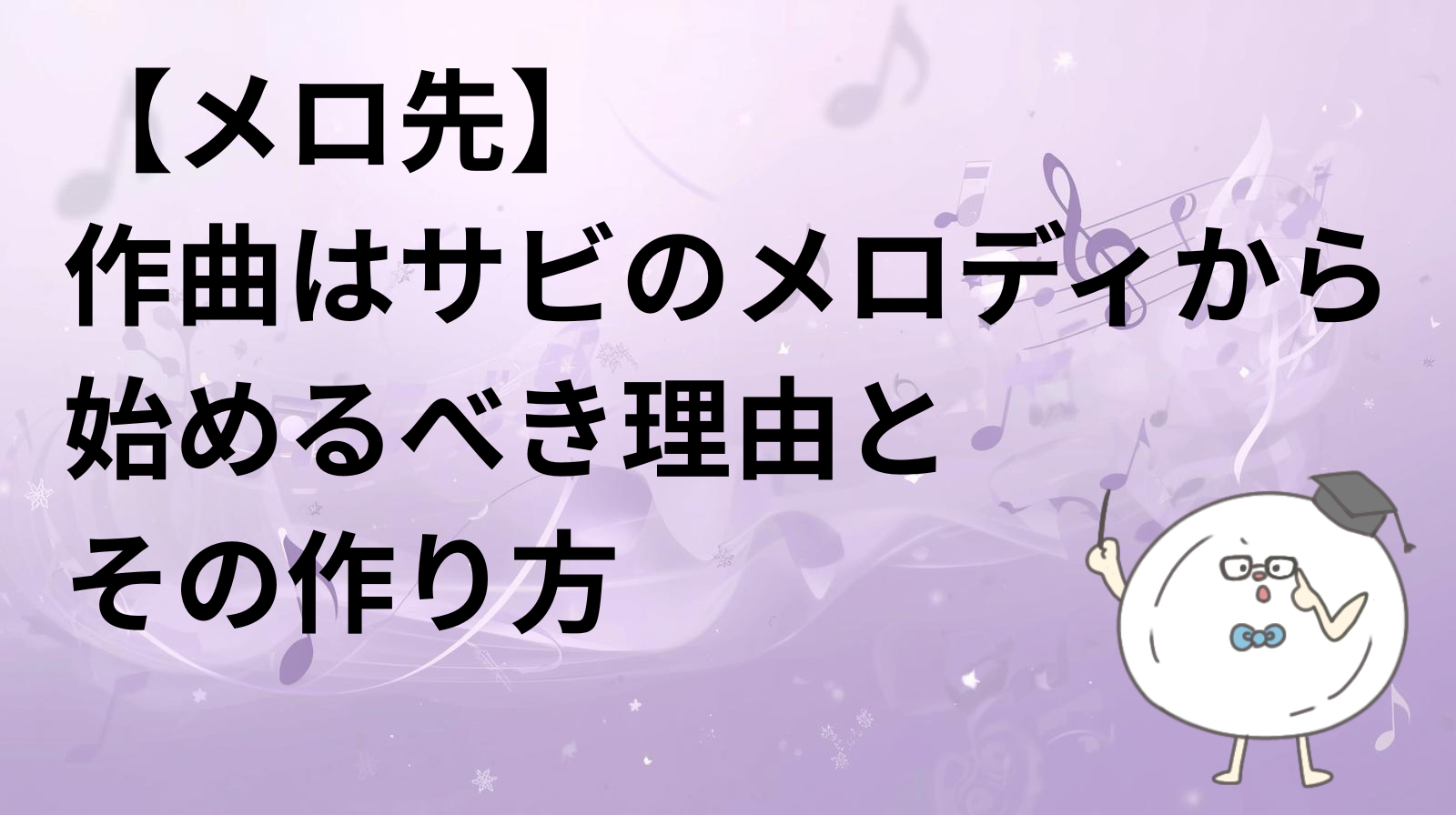
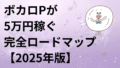
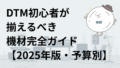
コメント